ラジオ翻訳の二回目。
今回も前回と同じくラジオチャンネル、MANGERの放送で、前回の翻訳と内容的にも通ずるものがあり、とても興味深かったものを扱いたい。
訳や解釈は筆者の見解であり、うまく理解できていない部分があることはあらかじめ断っておく。(直接引用でもパラフレーズして省略している部分も多め…)
今回扱うのは、「恥」と「食」について。少し哲学チックな内容だ。前回訳したラジオよりもよっぽど難しかった…
タイトルは、
Pourquoi avez-vous honte de manger seul.e ?(なぜ、あなたは一人で食事をとることに恥じらいを感じるのか。)
この問いの答えを探求するべく、ジャーナリストのLaurianne Melierre(ロリアンヌ・ムリエール)は哲学・神学の教授であるJean-Sébastien Philippart(ジョン=セバスチャン・フィリパール)に話を聞いていく。彼はまさに食卓と「一緒に食べること(manger ensemble)」の関係を研究対象の一つとしている。
なぜ一人で食べている人を見ると寂しい気持ちになるのか、耐えられなくなるのか。なぜ一人で食べていると、その寂しさをスマートフォンや本、音楽といったもので補おうとするのか。
そんな疑問の答えを探していく。
全部を訳すのは途方に暮れるため、タイトルの「なぜ、あなたは一人で食事をとることに恥じらいを感じるのか。」の答えになるように、前半18分を訳していきたい。
もちろんこれは、一人で入っても差し支えない、例えばスターバックスとか、マクドナルドとかそういう場所ではなく、れっきとしたレストランでの話であることを前提としている。
目次
まず「恥」という概念を理解しよう
恥。フランス語では「la honte」。ジャン=セバスチャンはこのように説明する。
恥とはなんでしょう。恥は、自分が邪魔ものだと感じることです。恥において一番つらいことは、自分がいたくないのにそこにいる、という状況なのです。
例えば青春期の若者たちは、自分のアイデンティティをグループに見出そうとします。それは少し自分を非個性化することでもありますが、もしグループが自分を排除しようとするのならそれは最悪です。(恥を感じます。)
つまり、一人で食べるということは、グループに属していない、ということになる。
青春期の人だけでなく、大人でさえも、一人で食べることに恥じらいを感じる。それはなぜなのか。
我々は「恥」という重荷を背負って生きなければなりません。
サルトル(Sartre)はラ・ノゼ(la nausée:吐き気)と呼びましたが、それを解決する方法は、自分の存在/居場所(la place)を探すことです。つまり、社会のどこかに自分の存在を認められるということ。
実存する孤独を解決するために、社会が私たちに居場所を与え、社会が自分の存在を証明するのですが、自分の居場所を見つけられない、あるいはほかの人に社会に排除されていると見られることは最悪な気分(terrible)になります。
社会における存在/居場所(place)という概念が、恥という気持ちと結びついていると説明している。
不安(insécurité)を感じることに大人や子どもという年齢は関係ないというのだ。グループや家族において居場所を見つけられないことは、排除されるということで、自分の孤独と向き合うことでもある。
ロリアンヌ・ムリエールは、このように補足している。
人はグループでいるように、一緒に食べて、寝て、そうやって進化してきました。
「コモンサリテ(commensalité)」という言葉をご存じでしょうか。「近しい人と一緒に食べる」というニュアンスの言葉です。comはラテン語で「一緒に(avec)」mensaは「テーブル(la table)」という意味を持っています。
誰かと一緒に食べることは生きるために必要不可欠なことなのです。
「複数人で食べる」は社会におけるアイデンティティ
家族や同僚、友人と食卓を囲むこと。それにはどんな意味合いがあるのだろうか。
ジャン=セバスチャンは「identité narrative(ナラティブとしてのアイデンティティ)」という言葉を用いながら、こう説明する。
グループで食べることは、一体感をもたらします。一緒にテーブルを囲むことは、統一感(unité)や連帯感(solidarité)、同一性/アイデンティティ(identité)を保てるかどうかにかかっているのです。アイデンティティというのはナラティブとしてのアイデンティティですが。
(中略)
一人で孤独に食べている人は、疎外されている人、という認識が起こるのです。まるでゲームに参加していない人のように。
つまり、
複数人で食べるということは、グループ、団体としてのアイデンティティを生み出し、その関係性を強めたり、友好関係を永続させたりするという意味がある
というのだ。そして、うまくこの一体感を感じたときには、幸せな気持ちや、社会に認められたような気持ちになるという。
反対に、
一人で食べるということは、「属している」という気持ちをつくり上げているプロセスを断つということ
と説明している。
「一人で食べている=気の毒」という認識はどう形成されたのか
ロリアンヌ・マリエールは、「一人で食べている人が気の毒で、孤独である、ということは学ぶわけでもないのに、どうして無意識のうちにそういう判断をしてしまうのだろうか」と問う。
ジャン=セバスチャンはこう答える。
食卓(la table)は、教育にとって重要な役割を持っているのです。それは一つの社会性を帯びていて、子どもたちはそこから学んでいきます。
食卓に座った人は、その席に座っているという物理的な存在に加え、一人一人が食卓においての役割を持っていると子どもながらに認識しています。
子どものうちは複数人で食卓を囲むのが当たり前だからこそ、一人で食べている大人を見ると、違和感を覚えるのです。
しかし、理由はこれだけではない。西欧のユダヤ・キリスト教文化が大きく関係しているという。ロリアンヌ・マリエールはこう説明する。
ユダヤ・キリスト教の文化は、食事のイメージを形成してきたのです。イエスが「これはわたしの身体わたしの血である」と言ってパンとワインを分け与えたことに始まり、アガペーでは、性別や社会階級を問わずみんなが一緒になってお祝いし、食事を分かち合います。
このキリスト教の慣習は、共同体の考え方と密接に結びついています。
※アガペー(愛餐)は、キリスト教会で、礼拝のあとに信徒が共にする食事のこと(大辞林)。
続いて、ジャン=セバスチャンはキリスト教が一人で食べることをどのように見ていたのか、ということを説明する。
まず、一人で食べている人を食卓に招き入れたという。特にこれは外国人を受け入れる文化があった。
そうでなければ、共同体や友愛という考えがない者として軽蔑していたという。それは、キリストがヒューマニティ(humanité)は分かち合う(partager)ことにあるとしていたからである。
まとめ
以上のインタビューからわかるように、食卓を複数で囲む、ということには一体感を生み、友情や人との関係を築くという意味において重要であるとされている。
子どものころから一緒に食べることが当たり前であり、さらに食卓を囲む一人一人が役割をもってそこに存在していると認識されることが、「一人で食べる=孤独、気の毒」というイメージを作っている。
聖書には「Manger c’est partager」(食べるということは分かち合うということである)と書かれているのだそうだ。
共同体(communauté)が重要なものとされているキリスト教においては特に、一緒に食べること、分かち合うということが文化として根付いているのである。
訳してみた感想
自分自身のことを思い返してみると、確かにカフェやレストランに一人で行くと、隣の人と話したいなあ、と思うことがある。
この本を読もう、と読書を目的にカフェに行くこともあるが、カフェに行くこと、コーヒーを楽しむことが目的なのに、おもむろに本やスマートフォンを出している自分がいることもある。
自分が「恥」という気持ちを感じているとは認識してはいなかったが、グループでディスカッションをしている際、自分が意見を言えないと何となく居心地が悪くなることもあった。その空間にいる意味を見出せず、まさに「ゲームに参加していない人」という気持ちになってしまう。それは、大いに共感できた。
ただ、食卓における「恥」は、日本ではどうなのだろう、と考える。
コモンサリテのような文化は強くないし、一人で食べること、「おひとり様」も、マーケティングの決まり文句のようになっている。もちろん、高級なレストランは一人で予約が取れない場合もあるが。
キリスト教の影響も少なく、「食事中はおしゃべりをしない」というマナーが存在する日本では、もしかしたらフランスとはまた違った、食卓をめぐる心理状態が存在しているのかもしれない。
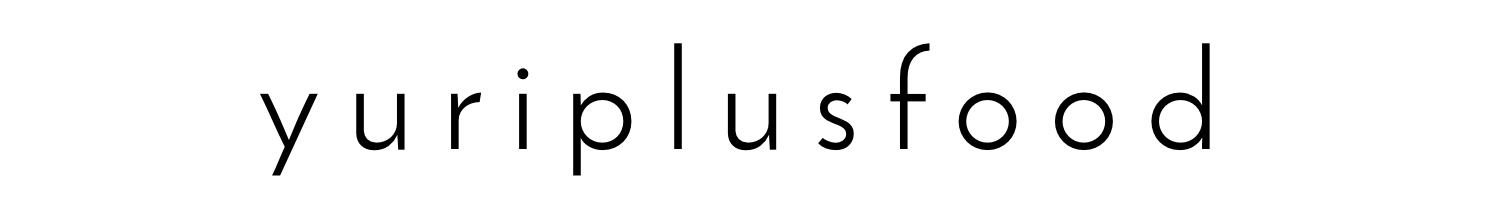






コメントを残す